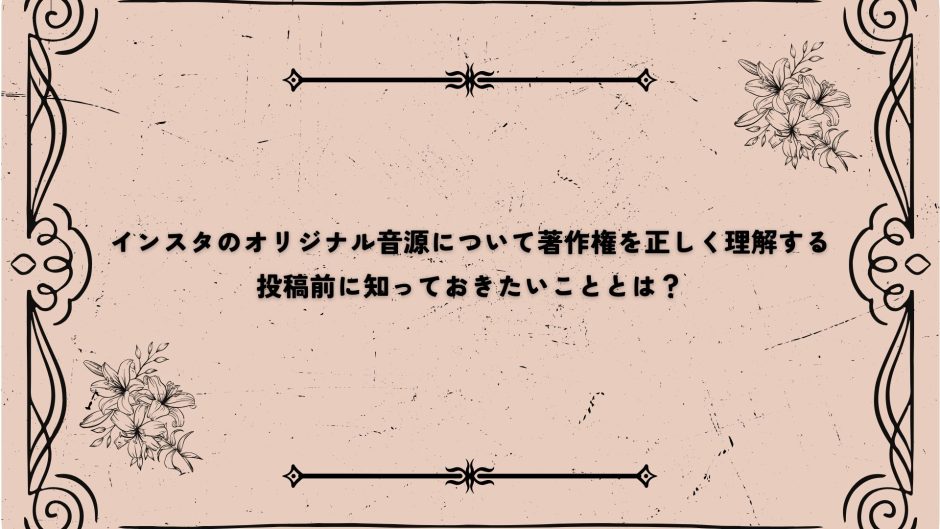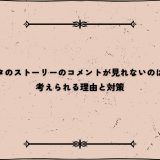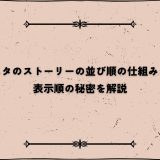インスタグラムで「オリジナル音源」を使った投稿が注目を集める一方で、「著作権は大丈夫?」と不安に思う方も増えています。実は“オリジナル”と言っても、すべてが著作権フリーとは限りません。
本記事では、インスタ上での「オリジナル音源」の定義や誤解されやすいポイント、音源使用のルールや注意点を、アカウントの種類別にわかりやすく解説します。
目次
- 1. はじめに:なぜ今“オリジナル音源”が注目されているのか?
- 2. オリジナル音源とは何か?インスタ上での定義と誤解
- 3. インスタでの音源使用ルールの全体像
- 4. アカウント別|インスタで音源使用時に気をつけるべき制限
- 5. インスタ投稿における「オリジナル音源」使用時のチェックリスト
- 6. よくある誤解とNG行為|オリジナル音源でも起きる著作権違反
- 7. オリジナル音源を守る|自作音源の著作権保護・登録ガイド
- 8. フリー音源との違いと使い分け|“無料”と“オリジナル”はどう違う?
- 9. 実例で学ぶ:オリジナル音源を活用してバズったインスタ投稿5選
- 10. 著作権侵害のリスクと対処法
- 11. Q&A:インスタでのオリジナル音源使用に関する疑問解消
- 12. まとめ:安心してオリジナル音源を活用し、魅力的な発信をしよう
1. はじめに:なぜ今“オリジナル音源”が注目されているのか?
「インスタの投稿でBGMを使ったら、突然音が消えちゃった…」
「せっかく作った動画が著作権違反で削除されてしまった…」
こんな声、最近とても増えているんです。
背景には、Instagramの著作権管理が年々厳しくなってきていることがあります。
特に2025年に入ってからは、ビジネスアカウントや広告投稿に対しての音楽利用制限が強化され、ユーザーの間で混乱が広がっています。
でも、そこで注目されているのが「オリジナル音源」なんです。
自分で作った音楽や効果音、ボイスなどを使えば、著作権に怯えることなく投稿が可能になります。
しかも、最近では無料の音楽制作アプリや編集ソフトも増えていて、専門知識がなくても手軽にオリジナル音源が作れる時代になっています。
また、Instagramの仕組み上、「どの音源を使ったか」は自動でチェックされています。
たとえば、スマホに入れていた市販の楽曲を動画に載せたら、それだけでAIに検知されて投稿がブロックされたり、最悪の場合はアカウント停止という重いペナルティを受けることもあるんです。
だからこそ、今「安全に投稿したい」「アカウントを守りながら表現したい」と考えるユーザーにとって、オリジナル音源の価値はとても高まっているんですね。
特に以下のような人には、オリジナル音源がピッタリです。
- Instagramで商品やサービスを紹介している人
- 店舗や教室のプロモーションを投稿している人
- トレンドに流されない“自分らしい発信”をしたい人
さらに、Meta社と世界の大手レーベルとのライセンス契約によって、インスタの「ミュージックライブラリ」に収録されている楽曲のみが安心して使えるのですが、そのラインナップはアカウントの種類によって異なるんです。
たとえば、ビジネスアカウントでは人気の音楽が検索に出てこないことがあるし、広告やプロモーション動画では、そもそも使用が制限されている曲もあります。
つまり、いくら好きな曲があっても、「使えない」ことがあるというわけです。
その点、オリジナル音源なら制限なしに使えて、しかも投稿の自由度もアップ。
あなた自身のブランドや世界観を大切にしながら、安心して発信できるツールになるんです。
もちろん、「著作権フリー音源」や「パブリックドメインの楽曲」も選択肢のひとつですが、これらにも実は細かいライセンス条件があります。
「商用OKだけど、改変NG」「クレジット表記が必要」など、守るべきルールがあるのです。
だからこそ、オリジナル音源=“完全に自由に使える音楽”という位置づけで、注目度が急上昇しているのです。
今や、誰でも手軽に音楽を作って、誰でも発信できる時代。
あなたの声やメロディ、効果音が、Instagramの世界で唯一無二の魅力として輝くかもしれません。
さあ、“安心・安全”で“個性あふれる”投稿を始めるために、今こそ「オリジナル音源」の活用を真剣に考えてみましょう。
2. オリジナル音源とは何か?インスタ上での定義と誤解
Instagramで「オリジナル音源」と聞くと、多くの人が「自分で作ったものなら自由に使える」と思ってしまいがちです。でも実は、インスタ上で“オリジナル”と表示される音源が必ずしも著作権フリーとは限らないんです。このセクションでは、「オリジナル音源」の種類と定義、そしてそこに潜む誤解や注意点をやさしく、丁寧にお伝えしていきますね。
2-1. オリジナル音源の種類|自作BGM/友人の演奏/ボイス/AI生成など
インスタに投稿する音声コンテンツには、さまざまな「オリジナル音源」があります。以下のようなものが代表的です:
- 自作BGM:自分でDTM(音楽制作ソフト)などを使って作曲・録音した音楽。
- 友人の演奏:ギターやピアノなどの演奏を録音して投稿。
- ナレーション・ボイス:自分の声で話したり、歌ったりした音声。
- AI生成音楽:AIツールで作られた音源を利用。
これらはいずれも「誰かの既存の曲を使っていない」ため、いわゆる「オリジナル」と認識されがちです。しかし、“オリジナル”=“著作権トラブルが起きない”とは限らないのです。
たとえば、AIで生成された楽曲でも、使っている素材に第三者の著作物が混ざっていたら、それは立派な著作権侵害になりえます。また、友人の演奏であっても、演奏している曲が有名アーティストのものであれば、その曲の著作権をクリアしなければいけません。
2-2. 「オリジナル=著作権フリー」ではない理由
「オリジナルなら自由に使えるはず!」というのは、実はよくある誤解です。Instagramが「オリジナル音源」と表記していても、それは単に「インスタに初めてアップされた音源」だという意味でしかありません。
つまり、「著作権フリー」や「ライセンス済み」という意味ではないのです。たとえば、市販CDの音楽を動画に挿入して投稿してしまった場合、それがたとえインスタ上で“オリジナル”と表示されても、著作権侵害に該当します。
さらに怖いのは、本人が気づかずに違反してしまっているケースが多いこと。「友達が作ったから」「AIが生成したから」と安心していても、どこかで既存曲のメロディが混ざっていたらNGなんです。
正確には、「著作権者に使用の許可を得ていない音源」は、たとえオリジナルっぽく見えても著作権違反になる可能性があるということを覚えておきましょう。
2-3. 無断使用と“オリジナル”の境界線|実際に起きたトラブル例
では実際に、“オリジナル音源”を使ったつもりがトラブルになった事例には、どのようなものがあるのでしょうか?以下のようなケースがあります。
- ケース1:スマホに保存していた有名曲の一部を加工して投稿。
インスタ上では“オリジナル音源”と表示されたが、実際は無断使用だったため、投稿が削除されてしまった。 - ケース2:友人が演奏したクラシックの楽曲をリールに使用。
原曲は著作権切れだったものの、演奏そのものには著作隣接権が発生しており、演奏者からクレームを受けた。 - ケース3:AIで生成したメロディを投稿したが、似た構成の既存曲と一致。
音楽管理団体の自動検出に引っかかり、著作権侵害の警告が届いた。
こうした事例からわかるのは、「本人が意図していなくても違反になる」という怖さです。
特にAI生成や外部編集アプリで音楽を加える場合、自分で作ったと信じていても、素材の中に他人の著作物が含まれていることがあるため、注意が必要です。
また、「オリジナルだから、どこかで聞いたことのある曲の雰囲気で作っただけ」という感覚も危険です。著作権法では、“類似”や“翻案”でも侵害と見なされる可能性があるからです。
2-4. まとめ|「オリジナル=安全」は大間違い!
インスタでの「オリジナル音源」は、必ずしも著作権的にクリーンな存在ではありません。たとえ自作やAI生成であっても、使用した素材や元の楽曲に問題があれば、著作権違反になる可能性があるのです。
だからこそ、音楽を使うときは「誰が作ったか」だけでなく、「何を使って作ったのか」「元になったメロディがあるか」などにも注意を払いましょう。
インスタで安心して音楽を楽しむためには、「オリジナル=安心」と思い込まないことが、最大の予防策です。音楽を味方に、トラブルのない楽しい投稿を続けていきましょうね。
3. インスタでの音源使用ルールの全体像
Instagramで音楽を使うときに一番大切なのは、「その音源が合法に使えるものか」をきちんと理解しておくことです。知らずに使ってしまった音楽が原因で、投稿が削除されたり、アカウントが制限されたりすることもあります。ここでは、音楽の著作権の仕組みやInstagramがどのように音楽を使えるようにしているか、そして自動検出システムの仕組みまでをわかりやすく解説します。子どもでもわかるように、順を追って丁寧に説明していきますね。
3-1. 著作権の基本構造|作詞・作曲・演奏・録音それぞれの権利
まず、音楽の著作権ってなに?というところから見ていきましょう。音楽には実は4つの異なる権利が存在しているんです。
1つ目は作詞者の権利。歌詞を書いた人が持つ権利です。2つ目は作曲者の権利。メロディやコード進行を作った人のものです。3つ目は演奏者の権利。たとえばギターを弾いたり歌ったりした人ですね。そして4つ目が録音した人の権利。CDやデータに音楽を保存した会社などがこれに当たります。
つまり、音楽を使うというのは「曲を聴く」だけじゃなく、複数の人の努力と権利が重なっているということなんですね。それをInstagramに勝手にアップすると、誰かの大切な権利を傷つけてしまうかもしれません。
3-2. インスタで音楽が使える仕組み|Metaと音楽レーベルの契約
「でも、インスタって普通に音楽を選んで使えるよね?」と思うかもしれません。はい、その通り。Instagramではミュージックライブラリという機能を使って、たくさんの音楽を選んで投稿に加えることができます。でもこれは、裏で大きな仕組みが動いているからできることなんですよ。
Instagramの親会社であるMeta(旧Facebook)は、ユニバーサル・ソニー・ワーナーなどの世界的な音楽レーベルと契約を結んでいます。その契約によって、決められた曲だけがInstagramで公式に使えるようになっているんです。
そしてこの仕組みは、国やアカウントの種類によって使える範囲が変わるという点も覚えておいてください。たとえばビジネスアカウントでは、人気アーティストの曲が使えなかったりするんですね。それは「商用利用」が制限されているから。投稿の内容や目的によって使える音楽が変わるので、注意が必要です。
3-3. インスタの音楽自動検出システムの実態と制限例
そして、Instagramでは音楽の自動検出システムが働いています。これがあるおかげで、違法に使われた音源がすぐに見つかってしまうんですね。
たとえば、市販のCDから取り込んだ音楽や、YouTubeからダウンロードした曲を動画に入れて投稿した場合。インスタのシステムはその音源を聞き分けて、「許可されていない音楽です」と判断し、自動で投稿を削除することがあります。
また、「曲のテンポを変えたから大丈夫」「短く編集したからバレない」と思っていても危険です。このシステムは、速度を変えたり一部を加工した音楽でも検出してしまうほど高性能。「ちょっとだけならOK」という考えは通用しないと思っておきましょう。
さらに注意が必要なのが、ビジネスアカウントでの商用利用です。たとえば商品を紹介する動画にトレンド音楽を使ったり、店舗の紹介にBGMをつけると、「この音楽は商用利用できません」と判断されることがあります。これは、Metaとレーベルの契約に「非商用のみ」といった制限があるためなんです。
その結果、投稿がブロックされたり、音楽が勝手に消されたり、最悪の場合はアカウントが停止されてしまうことも。自動検出システムは私たちを守るものでもありますが、知らずに違反してしまうと大変なことになるんですね。
3-4 まとめ
Instagramで音楽を使うときは、「どの音源を、どんな形で使うか」をしっかり考えることがとても大切です。音楽には複数の権利者が関わっており、そのどれもが大切な財産。Metaが契約して提供している公式音源を選べば、著作権トラブルを防ぐことができます。
また、Instagramの音楽検出システムはとても精度が高く、無許可の音源や加工音源も見逃しません。ビジネスアカウントなどでは使用できる音楽が限られるため、アカウントの種類に合った使い方が求められます。
知らなかったでは済まされないのが音楽の著作権。インスタを楽しく安心して使うためにも、しっかりとルールを守って音楽を取り入れていきましょうね。
4. アカウント別|インスタで音源使用時に気をつけるべき制限
4-1. 個人アカウント:非商用利用でもNGになるケース
個人アカウントだからといって、音楽の使用に関して完全に自由というわけではありません。Instagramでは、非商用利用を前提に音楽機能を提供していますが、それでも著作権を無視した使い方はNGです。
たとえば、自分のスマホに入っている市販の楽曲を、編集アプリで動画に挿入して投稿する行為は、著作権侵害と判断される可能性があります。これは、「Instagram内の音楽機能を通じて追加した音源」しか安全ではないというルールがあるからです。
また、個人アカウントであっても、フォロワーが多く、影響力のある投稿と見なされた場合、商用性を疑われて制限を受けることもあります。ライブ配信中にBGMを流してしまい、自動的に音声がミュートされたという事例も多く報告されています。
「ちょっとだけ」「個人利用だから大丈夫」という油断が、投稿削除やアカウント制限につながることもあるため、公式ライブラリの音源を使うのが安心です。
4-2. ビジネスアカウント:広告投稿やPR動画の著作権的注意点
ビジネスアカウントを運用している場合は、音楽の利用が最も制限されるアカウント種別です。Instagramでは、ビジネス用途と見なされた投稿について、一部の人気楽曲や有名アーティストの音源が表示されなくなる仕様となっています。
その背景には、Instagramの親会社であるMetaが結んでいる音楽ライセンス契約があります。この契約は非商用目的に限った楽曲利用を前提にしているため、ビジネス投稿には適用されない場合が多いのです。
たとえば、店舗紹介動画にトレンド曲をつけた投稿や、ライブ配信中にCD音源を流してしまう行為は、著作権違反として自動検出され、音声が削除されたり、投稿自体がブロックされることもあります。
広告やプロモーションの目的で音楽を使いたい場合は、ロイヤリティフリーの音源や、商用利用が許可されたフリーBGMを選ぶのが安全です。動画編集時には、使用している音源のライセンス条件を必ず確認しましょう。
4-3. クリエイターアカウント:オリジナル音源の戦略的活用法
クリエイターアカウントは、個人アカウントとビジネスアカウントの中間に位置する存在で、柔軟に音楽機能を使える点が特徴です。特に、インフルエンサーやアーティストなど、自己発信力の高いユーザーに適した設定となっています。
このアカウントでは、Instagram公式ライブラリのトレンド曲も比較的自由に利用できるため、リール動画での発見性も高まりやすくなります。
一方で、企業案件や商品のPRを含む投稿では、ビジネスアカウントと同様に商用扱いされる可能性があるため、使用する音源には十分な配慮が必要です。
おすすめなのは、自作のオリジナル音源を使うことです。これにより、ブランディング効果が高まり、他の投稿との差別化にもつながります。無料の録音アプリやDAW(音楽制作ソフト)を活用して、自分だけのサウンドを作るのも楽しいですよ。
4-4. 海外アカウントとの違い:地域別の使用可否と表示制限
Instagramの音楽機能は、実は地域ごとに利用可能な楽曲が異なることをご存知でしょうか?同じアカウントでも、アクセスする国や地域によって音源の表示・使用が制限される場合があります。
たとえば、アメリカのアカウントでは利用可能だった音源が、日本のアカウントでは非表示になるといったケースも珍しくありません。これは、Meta社が国ごとに結んでいる音楽ライセンス契約の範囲が異なることが原因です。
また、Instagramで使用される音楽には、配信対象の国が限定されているものもあるため、海外の音源を使った投稿が日本ではブロックされてしまう可能性も。
さらに、日本国内ではJASRACやNexToneといった著作権管理団体の規制が厳しいため、海外よりも制限が強い傾向にあります。
そのため、海外のトレンド音楽を使いたい場合は、VPNを使った操作や、音源のライセンスを直接確認するなど、慎重な対応が求められます。地域制限によるトラブルを避けるためにも、自分のアカウントが属する地域で使用可能な音源を把握しておくことがとても大切です。
5. インスタ投稿における「オリジナル音源」使用時のチェックリスト
Instagramでオリジナル音源を使って投稿することは、他人と差をつける素敵な方法です。
でも、音楽にはたくさんの著作権のルールがあり、「自作だから大丈夫」と安心するのは危険です。
ここでは、インスタにオリジナル音源を使うときに、絶対に確認しておきたい4つのポイントをわかりやすく紹介します。
「思わぬ違反で投稿が削除される…」なんてことにならないように、しっかりチェックしていきましょう。
5-1. 他人の演奏・歌声を使っていないか?(著作隣接権)
たとえ楽曲自体は自分で作曲した「完全オリジナル」だったとしても、演奏した人や歌った人が他人であれば、その人にも“著作隣接権”という権利が発生します。
つまり、勝手に友達の歌声や演奏を使って投稿すると、著作権侵害になってしまうことがあるのです。
実際にInstagramでは、「友達が弾いたギターを録音しただけだから大丈夫と思って投稿したら、音源が削除された」というケースもあります。
演奏者・歌い手から使用の許可を得ているかを、必ず確認しましょう。
また、後々トラブルにならないよう、メッセージや録音アプリでの同意証拠を残しておくこともおすすめです。
5-2. 商用利用とみなされる可能性がないか?
オリジナル音源を使って投稿する際に特に注意したいのが「商用利用とみなされるかどうか」です。
Instagramは、投稿の内容やアカウントの種類によって、「これはビジネス目的の投稿だな」と判断することがあります。
たとえば、自作のBGMを背景にして自分のショップ商品を紹介した場合、それは完全に“商用利用”とみなされる可能性が高いのです。
Instagramでは、ビジネスアカウントでの音楽使用は厳しく制限されており、有名アーティストの曲だけでなく、自作音源でも制限対象になることがあります。
だからこそ、たとえオリジナルでも、商用で使用する際にはライセンスの明示や、投稿の文脈に注意を払う必要があります。
「収益目的で音源を使っていないか?」という視点で、投稿前に自問自答してみましょう。
5-3. 類似曲によるメロディの侵害リスクは?
「自分で作ったメロディだから大丈夫」と思っていても、既存の楽曲に似ていた場合、それだけで“著作権侵害”と判断されるケースがあります。
特にメロディラインが有名な楽曲と似ていたり、サビの部分に共通点が多いと、思わぬクレームを受ける可能性も。
JASRACやレーベルは音源の監視を強化しており、AIで自動検出された類似性がトラブルの引き金になることもあります。
もし作曲したメロディに心当たりがある場合は、ネット上で一度検索して似た曲がないかを確認する、音楽制作アプリの“類似チェック機能”を活用するなど、リスク回避の工夫が大切です。
「知らなかった」では済まされない世界なので、慎重に進めましょう。
5-4. 使用した音源に“ライセンス違反素材”が含まれていないか?
オリジナル音源を制作する際に、フリー音源やサンプルパック、効果音素材などを使った場合は要注意です。
こうした素材の中には、「商用利用不可」「SNS使用禁止」など、厳しいライセンス条件が設定されていることがあります。
たとえば、有名な効果音サイトでダウンロードしたSE(効果音)を使ったとしても、クレジット表記が必要だったり、加工が禁止されているケースがあります。
Instagramは投稿後に音源の出どころを確認することができないため、万が一ライセンス違反があった場合は、動画が削除されたり、アカウント制限がかかるリスクも。
「フリー素材=自由に使える」と思わず、必ずライセンス条件を読んで、投稿目的に合っているか確認することが重要です。
不安な場合は、ライセンスが緩やかな「完全著作権フリー素材」や、自分で録音した効果音を使うのが安全です。
6. よくある誤解とNG行為|オリジナル音源でも起きる著作権違反
インスタグラムで「オリジナル音源だから大丈夫」と思っている人は、もしかすると重大な落とし穴にはまっているかもしれません。自分で作った音楽や加工したサウンドであっても、著作権のルールを知らないと違反になってしまうことがあるのです。ここでは、ありがちな誤解と実際に違反となるNG行為をわかりやすく解説していきます。子どもにも説明できるくらい、ひとつひとつ丁寧にお話ししますね。
6-1. DAWの無料サンプル素材をそのまま使うのはNG?
音楽制作に使われるDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)には、便利なループ素材や効果音がたくさん入っています。これをそのまま使えばオリジナルだと思ってしまいがちですが、実はこれ、要注意なんです。
たとえば、GarageBandやLogic Pro、FL Studioなどに付属している無料サンプル素材は、ライセンスにより「商用利用可」とされている場合もあります。しかし、それらを切り貼りしただけで、創作性がほとんどないままインスタで投稿すると、著作権上「オリジナル」とはみなされないことがあります。
また、他のクリエイターが同じサンプルを使って楽曲を投稿していた場合、コンテンツの重複としてAI検出されるリスクも。自分で音を作り込むなど、独自性を加えることが著作権回避のためにも大切です。「使える」と書かれていても、「創作性の有無」が判断基準になることを忘れないでくださいね。
6-2. AI作曲ツールで作った音源に著作権はあるのか?
最近はAI作曲アプリやサービスがとっても便利ですよね。でも、AIが作った音楽には著作権があるのかどうか、疑問に思ったことはありませんか?
実は、AIが完全に自動で生成した音楽には「著作権がない」とされるケースもあるんです。日本の著作権法では「人間の創作活動」に基づいていることが条件になるため、人の手が一切加わっていないAI生成物は、法律上の著作物として保護されないことがあります。
とはいえ、AIが提案したメロディに自分でアレンジや歌詞を加えた場合には、そこに「創作性」が生まれ、著作権が発生する可能性があるんですよ。つまり、AIツールは「素材」として活用し、自分の手で仕上げるのがコツ。完全な自動生成音源を「自作」と言って投稿すると、トラブルの元になるので要注意です。
6-3. 他人の曲に自分の歌詞を乗せて投稿するのは違法?
「メロディは有名な曲だけど、歌詞は自分で考えたからOK!」このように思っていませんか?実はこれ、著作権的にはNGなケースです。
音楽には「作詞」「作曲」「編曲」「演奏」など、いくつもの権利が複雑に絡んでいます。メロディ(作曲部分)に他人の権利がある以上、自分の歌詞をつけただけでは著作権侵害を回避できないんです。
とくにインスタグラムのようなSNSで公開する場合、著作権者の許可がないと配信・公開の段階で違反とされる可能性が非常に高いです。無断で投稿したことでアカウント停止になった事例も報告されています。どれだけオリジナルの歌詞でも、メロディが他人のものであれば、投稿前に必ず権利を確認しましょう。
6-4. フリー素材に自分の声を重ねたら“オリジナル”になるのか?
「フリーBGMを使って、自分の声をのせたからオリジナルでしょ?」これもよくある誤解です。
フリー素材は、たしかに誰でも使えるように公開されています。でも、その「使い方」にはルールがあります。自分の声を重ねただけでは、そのBGMの著作権が消えるわけではないんです。
たとえば、「クレジット表記が必要」や「商用利用NG」など、素材ごとにライセンス条件が異なります。声を重ねても元のBGMの著作権表示義務が残る場合があるので、ライセンスをしっかり読まないとトラブルになります。
また、編集アプリで加工しても、それが「改変不可」と書かれていれば違反になります。声を重ねる=オリジナル化、ではなく、「二次創作」の一種になることもあるんですよ。ルールを守って初めて、自由に楽しめるのがフリー素材なんです。
7. オリジナル音源を守る|自作音源の著作権保護・登録ガイド
インスタに投稿する音楽、自分でつくったから大丈夫!…そう思っている方も多いかもしれませんね。でも、せっかくのオリジナル音源が誰かに勝手に使われてしまったら、とっても悲しいですよね?自作の音源にも、しっかりと「著作権」を認識し、守る方法を知っておくことがとっても大切なんです。このセクションでは、自作音源の著作権についてわかりやすく解説していきますね。
7-1. 著作権は自動で発生するが、登録すべき理由とは?
「自分で作った曲や音、勝手に使われたら困る…でも著作権ってどう守ればいいの?」と心配になりますよね。実は、著作権は音源を「創作」したその瞬間に自動で発生するんです。つまり、登録しなくても法律的には保護されるんですよ。でも、ここで大切なのは「それが自分の作品だと証明できるかどうか」ということ。
万が一、誰かに盗用されたり、勝手に利用されてしまったとき、著作権登録をしておくことで証拠として使えるんです。特にInstagramでは、音源の盗用がこっそりと行われてしまうことも。そんなときに「これは私の音源です」と証明するための材料になるので、著作権登録はクリエイターにとって強力な武器になります。
7-2. JASRAC/NexToneへの登録方法と注意点
「登録って、どうやるの?」と思った方、大丈夫です。日本で著作権を管理してくれる主な団体は、JASRACとNexToneの2つがあります。どちらも音楽の権利を守ってくれる頼もしい味方です。
JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)では、作詞・作曲などを登録して、使用料の回収や著作権の管理を代行してくれます。申請には、楽譜や音源データ、歌詞などを提出します。審査に通れば、あなたの音楽が正式に管理対象となります。
NexToneは、特にインディーズやデジタル配信をメインに活動するクリエイター向けに親しみやすいサービスを展開しています。インターネット上の利用管理にも強く、YouTubeやInstagramでの音源使用が多い方にとって、とても心強い存在です。
ただし、どちらに登録する場合も「商用利用・配信範囲・管理の範囲」などをよく確認する必要があるんです。一度登録すると、契約期間中は自由に音源を動かせないこともあるので、内容はしっかり読んでから申し込みましょう。
7-3. 著作権登録以外の音源保護法|タイムスタンプ/商標登録との違い
「登録まではしないけど、証拠だけ残しておきたい…」そんなときにはタイムスタンプサービスを使う方法もあります。これは、音源をつくった日付やファイルの内容を第三者機関が記録してくれるしくみ。後から「この音源は私のものです」と証明するための、有力な手段になります。
たとえば、「e-文書タイムスタンプ」や「INPITの公証サービス」などがあります。これらは著作権の法的登録ではありませんが、裁判などで著作物の存在証明として活用できることがあります。
また、「音源の名前やアーティスト名」を守りたい場合は商標登録も選択肢に入ります。ただし、商標は「商品やサービスに使う名前・マーク」を守るための制度なので、著作権とは目的が異なります。音源そのものの創作権利を守るなら著作権登録やタイムスタンプがベストです。
7-4. 音源盗用時の対処法と相談窓口(文化庁/弁護士費用相場)
せっかく作った音源が、誰かに勝手に使われてしまったら…それは大問題。そんなとき、どうすればいいのか知っておくと安心ですよ。
まずは「証拠を確保」することが大切です。盗用された投稿のスクリーンショットや動画、アップロード日時など、記録できるものは全部残しておきましょう。
次に、文化庁の著作権相談窓口に問い合わせて、具体的な対応策を聞くことができます。また、知的財産に強い弁護士に相談するのも一つの方法です。最近では、初回相談が無料の法律事務所も多く、著作権のトラブルに特化したサポートも受けられます。
弁護士費用は、簡単な相談であれば1時間あたり5,000〜10,000円前後が相場ですが、トラブルの内容によっては成功報酬型になることもあります。事前に見積もりを出してもらえる事務所を選ぶと安心です。
「大ごとになるのが怖い…」と感じるかもしれませんが、自分の作品を守るのはとても大切なこと。専門家の力を借りながら、しっかりと対処していきましょう。
8. フリー音源との違いと使い分け|“無料”と“オリジナル”はどう違う?
8-1. 著作権フリー音源の仕組みと利用条件
「著作権フリー音源」と聞くと、なんでも自由に使っていいと思ってしまいがちですが、実はそうではありません。本当の意味で“著作権が完全にない”音源はほとんど存在しません。多くの場合、これは「ロイヤリティフリー(使用料無料)」という意味で、事前に決められた条件さえ守れば、追加料金なしで繰り返し利用できる音楽素材のことを指します。
たとえば「YouTubeオーディオライブラリ」や「甘茶の音楽工房」といったサイトで配布されているBGMには、「商用OK」「クレジット表記必要」「改変不可」などのライセンス条件がついていることが多いです。つまり、「無料で使える」とは言っても、「完全に自由」ではないということ。条件をしっかり確認しないまま投稿に使うと、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
特にInstagramに投稿する場合は、編集アプリで音源を加えてアップロードすることになるため、インスタ側での著作権処理がされていない状態になります。そのため、利用する音源の出所とライセンス内容をきちんと理解しておくことが大切です。
8-2. オリジナル音源の方が安心・安全と言えるのか?
「だったら、自分で作った音源なら安心じゃない?」と思う方もいるでしょう。はい、その通りです。自作の音楽や、自分で録音したナレーション、効果音などは、著作権侵害の心配がなく、安全に使えます。
たとえば、自宅でギターを弾いた音をスマホで録音し、それをInstagramの投稿に使う。または、DAW(音楽制作ソフト)を使ってBGMを自作する。これらはすべて、著作権の心配がない“オリジナル音源”として利用できます。
特にビジネスやブランディングで使う場合、オリジナル音源は他者と差別化が図れたり、著作権処理にかかる手間を省けたりするため、とても有利です。また、近年はAI作曲ツールなども登場しており、手軽に音源を作成できる環境が整ってきています。
ただし、オリジナル音源でも、別の楽曲に似すぎていた場合や、第三者のメロディや音素材を取り込んでいた場合は、思わぬ著作権トラブルになることもあるので注意しましょう。
8-3. CanvaやCapCutで音源を追加した場合の扱いは?
最近はCanvaやCapCutのような動画編集アプリを使って、気軽に音楽付きの動画を作る人が増えていますよね。では、これらのアプリで追加した音源を使ってInstagramに投稿する場合、著作権的にはどうなるのでしょうか?
まず、CanvaやCapCutに収録されている音源も、それぞれのアプリと音源提供元との契約によって提供されているものです。そのため、アプリ内で使う分には問題なくても、Instagramにアップした時点でライセンスの適用範囲外になるケースがあるのです。
たとえば、Canvaの無料プランで使えるBGMは、非商用目的での使用に限定されているものが多く、ビジネスアカウントで使うと著作権侵害になる可能性があります。CapCutも同様で、TikTokと連携した使用には強いですが、Instagramへの再投稿では制限を受ける場合があります。
つまり、「アプリで使えたからInstagramでも大丈夫」という考えは危険です。投稿前にライセンスをしっかり確認し、商用利用や外部SNSでの利用が許可されている音源だけを使うようにしましょう。
8-4. 商用利用前提ならどちらを選ぶべきか?
ビジネスアカウントでの投稿や、プロモーション動画の制作など、商用利用を前提とする場合は「フリー音源」と「オリジナル音源」のどちらを選べば良いのでしょうか?
結論から言うと、最も安心なのは「自作のオリジナル音源」です。ただし、音楽制作のスキルや時間が必要になるため、誰でもすぐに取り組めるわけではありません。そのため、現実的な選択肢としては、商用利用可能な著作権フリー音源を、正しくライセンス条件を確認したうえで使うのが安全です。
たとえば、「Artlist」や「Epidemic Sound」などの有料ライブラリは、商用利用を前提としたライセンス契約が整っており、インスタ広告や企業アカウントでも安心して使用できる音源が多数揃っています。一方、無料サイトを利用する場合でも、クレジット表記や再配布不可などの条件をきちんと守れば、コストを抑えつつリスクも回避できます。
商用利用では、「安心・安全」が何よりも重要。万が一、投稿が削除されたりアカウントが制限されたりすると、ビジネスに大きなダメージが出る可能性があります。使用する音源のライセンスを確認するクセをつけて、リスクのない投稿運用を心がけましょう。
9. 実例で学ぶ:オリジナル音源を活用してバズったインスタ投稿5選
Instagramでは、著作権に配慮しながら音楽を使う工夫が注目されています。特にオリジナル音源を活用した投稿は、著作権侵害を回避するだけでなく、ブランディングやバズ効果にもつながる強力な武器になります。ここでは、実際にインスタでオリジナル音源を使って成功した5つの事例をご紹介します。著作権の基礎を踏まえたうえで、どんな音源利用が有効だったのか、ぜひ参考にしてくださいね。
9-1. 小規模アカウントがBGM自作でバズった成功例
とあるフォロワー300人未満のイラストレーターが、自宅で録音したピアノBGMを使って投稿した動画が、わずか3日で再生回数3万回を超えた例があります。音源はGarageBandを使って制作し、動画には制作過程のタイムラプスを組み合わせました。著作権侵害を避けながらも「自作音源ならではのオリジナリティ」がフォロワーの心をつかみ、保存・シェアも多く発生したのです。
この投稿ではInstagram公式ライブラリに頼らずに音楽を用意したことで、他の投稿との差別化ができました。さらに、ビジネスアカウントであっても制限を受けない音源という点で、非常に賢い戦略でした。
9-2. ブランドPRにオリジナル音源を活用した戦略事例
使用したのは、プロの作曲家に依頼して制作した20秒のインストゥルメンタル音源。リズム感がよく、テンポも程よいため多くのユーザーがこの音源を使って参加投稿を行いました。
「音源の使いまわしによるトレンド形成」が起きやすいのは、まさにオリジナルBGMの魅力です。他の投稿と重複しないことで、ブランディングと共感の両立に成功しました。商用利用でも問題ない自社制作音源で、著作権上のリスクを完全に回避できた点もポイントです。
9-3. トラブルを回避した“カバー風”投稿の工夫
歌のカバーを投稿したいけれど、著作権が気になる…という悩みを解決したのが、あるボーカリストの工夫です。彼女は、有名曲のメロディを一切使わずに、雰囲気だけを似せた“カバー風オリジナル曲”を自作して歌唱し、インスタにアップ。曲調は似ていても、完全に別曲という構成により、著作権リスクを避けながら「〇〇風の歌」として注目を集めました。
このように、「雰囲気を演出しながら、内容は独自に構成する」という工夫は、音楽投稿での新しい選択肢です。音楽の改変や無許可使用に該当しないため、リスク管理の面でも非常に安心できます。
9-4. 有名クリエイターが守った著作権ポリシーとは?
登録者数10万人を超える音楽系インフルエンサーが、Instagramでの投稿において一貫して「自作音源のみ使用」をポリシーに掲げています。彼はすべての動画において、自ら制作・演奏した楽曲を背景音に使用しており、「音源提供します」という形でのコラボ依頼も多く受けています。
実は、Instagramでは「自作音源は最も安全な選択肢」の一つです。特にビジネスアカウントやPR案件を多く扱う場合、市販楽曲やレーベル音源の使用が制限される中で、自作音源なら一切の制限を受けずに済みます。このクリエイターの事例は、「著作権リスクゼロ」で活動を広げていくための良いお手本です。
9-5. 著作権侵害で炎上した投稿事例とその教訓
あるカフェのインスタアカウントが、新商品の紹介動画に有名アーティストの楽曲をBGMとして使った結果、著作権侵害で投稿が削除され、アカウントの一部機能が停止されました。投稿時には「誰も気にしないだろう」と軽く考えていたそうですが、動画が一気に拡散されたことでレーベル側のシステムに検出され、問題が発覚しました。
このケースから学べるのは、「バズる=バレる」ということ。音源が注目されるほど、著作権管理システムに引っかかるリスクは高くなります。たとえ小規模なアカウントでも、安心して音楽を使いたいなら「許可済音源か、自作BGM」を選ぶべきなのです。
9.6 まとめ
Instagramで音楽を活用した投稿を行う際には、著作権のリスクを理解したうえで戦略的に音源を選ぶことが大切です。特にオリジナル音源は、表現の幅を広げるだけでなく、安心して投稿できるという「自由と安全の両立」が可能です。
今回紹介した事例からもわかるように、「音楽の選び方次第で、投稿の未来は大きく変わる」のです。あなたの投稿がより多くの人に届くように、そして大切なアカウントが守られるように、音源の扱いには常に気を配りましょう。
10. 著作権侵害のリスクと対処法
Instagramで音楽を使うときに、一番気をつけてほしいのが「著作権侵害」。もし間違えて使ってしまったら、投稿が削除されたり、アカウントが凍結されてしまうこともあるんだよ。ここでは、著作権違反になったときにどうすればいいか、安心して使い続けるための方法をわかりやすく紹介していくね。
10-1. 著作権侵害で投稿削除された場合のフロー
もし投稿したリールや動画が、著作権違反で削除されちゃったら、まずは落ち着いて。Instagramでは、違反があった投稿に対して「削除通知」が届くの。この通知には、どの投稿が、どの理由で削除されたかが書かれているから、ちゃんと確認しようね。
たとえば、スマホで編集した動画に市販の音楽を入れて投稿した場合、Instagramのシステムがその音楽を検出して、自動で削除することがあるよ。このときにやることは次のとおりだよ:
- 通知をよく読む(英語で届くこともあるよ)
- 該当する投稿を削除、または非公開にする
- 同じ音楽を使った投稿を繰り返さない
削除された投稿をそのまま放置すると、Instagramからの信頼が下がって、将来的にアカウント制限や凍結のリスクが高まっちゃうんだ。だから、まずは通知にちゃんと対応して、ルールに合った音楽を使うようにしようね。
10-2. 「異議申し立て」はどう使う?正しいやり方
「この投稿、ちゃんとルールを守って作ったのに削除された!」っていう場合は、「異議申し立て」っていう機能があるよ。これは、自分の投稿が間違って削除されたと思ったときに使うものなんだ。
たとえば、自作のオリジナル音楽を使った投稿が削除された場合、ちゃんと証拠があれば、Instagramにそのことを伝えて、投稿の復旧をお願いすることができるんだよ。使い方はこんな感じ:
- 削除通知の中にある「異議申し立て」のリンクをクリック
- 「正当な理由」を入力(例:「この音源は自作です」)
- 許諾の証明がある場合は、内容を添えて送信
でも、なんとなく「大丈夫だと思ったから」という理由では、異議申し立てが通らないことが多いから注意してね。
明確な許諾がある場合や、Metaの公式音源ライブラリから選んだ音楽なのに間違って削除されたときなどに使うのが基本だよ。
10-3. アカウント凍結リスクと復旧できるかの判断基準
実は、著作権違反を何度も繰り返していると、Instagramのアカウント自体が使えなくなることがあるの。これを「アカウント凍結」って言うんだ。凍結されると、投稿はもちろん、フォロワーとのやり取りも全部できなくなっちゃうから、本当に大変なんだよ。
どんなときに凍結されるかというと:
- 著作権違反の投稿を何回も繰り返している
- 異議申し立てが通らなかった投稿がいくつもある
- 他人の音楽や映像を無断で使用している
1回だけなら警告で済むことが多いけど、2〜3回目になると凍結のリスクがぐっと上がるから、投稿ごとに慎重になってね。
もし凍結されてしまったら、Instagramの「ヘルプセンター」から異議を申し立てて、復旧をお願いすることができるよ。でも、復旧できるかどうかは違反の内容と回数によって違うから、やっぱり一番大事なのは最初からルールを守ることなんだ。
10-4. 投稿前に著作権チェックするツール・サービス一覧
「この音楽、使っても大丈夫かな?」って思ったときに使える、著作権チェックの便利なツールやサービスがいくつかあるよ。
以下は、特にインスタ投稿に役立つツールたち:
- Instagramミュージックライブラリ:投稿時にインスタ内で提供されている音楽だけを選べば、基本的に著作権の問題はなし!ストーリーやリールで「ミュージック」機能から探してね。
- YouTubeオーディオライブラリ:商用利用OKのBGMも多数あり。インスタ投稿用の動画に挿入してからアップできるよ。
- DOVA-SYNDROME(https://dova-s.jp/):日本語対応でわかりやすく、完全無料で利用できるフリー音源が豊富!
- OtoLogic(https://otologic.jp/):クレジット表記付きで、商用利用OKな音楽を多く提供しているサイト。
- Artlist / Epidemic Sound:有料だけど、高品質で商用利用にも安心な海外の人気音源サイト。
注意してほしいのは、「著作権フリー」って書いてあっても、使用条件があること。たとえば、「商用利用OKだけど、作者名を表記してください」とか「改変は禁止です」みたいな条件がある場合も多いんだよ。
投稿前に、ライセンス情報をしっかり読んで、「大丈夫!」と確認できてから使うようにしようね。
11. Q&A:インスタでのオリジナル音源使用に関する疑問解消
11-1. 著作権は本人確認ができれば発生するの?
著作権は、作品を創作した瞬間から自動的に発生します。つまり、あなた自身が音楽や歌詞を作った時点で、その作品にはあなたの著作権が存在するのです。これは特別な登録や申請がなくても成立します。
ただし、「誰が作ったか」が後から証明できるようにしておくことが重要です。たとえば、制作日時が記録されたデータを保存したり、自分宛に内容証明郵便で送っておいたり、クラウド保存しておくと後の証明に役立ちます。著作権トラブルになったとき、自分が著作権者であることを主張できる「証拠」があれば、安心です。
つまり、「本人確認ができれば発生する」のではなく、「創作された時点で発生し、その後に確認できる状態にしておくことが重要」なのです。子供が描いた歌やメロディでも、それがオリジナルなら立派な著作物になるんですよ。
11-2. 友達の曲に歌詞をつけてアップするのは違法?
これは著作権侵害になる可能性が非常に高い行為です。たとえ友達同士であっても、原曲を作ったのが友達であるなら、その曲には友達の著作権が存在します。そこに歌詞を勝手につけてインスタに投稿すれば、「無断改変」かつ「無断公表」になるおそれがあります。
著作権には「同一性保持権」という権利があり、勝手に作品を改変することは基本的にNGです。また、あなたがつけた歌詞自体にも著作権が発生するかもしれませんが、それでも元の音楽部分の著作権者の許可なく使えば違法となります。
もし「一緒に作った」という共同著作物であっても、投稿前にはお互いの同意が必要です。「友達だからいいや」では済まないので、しっかり許可をとりましょう。
11-3. 一部だけ流れてしまった市販曲は削除対象?
たとえ数秒でも市販曲が入ってしまえば、削除される可能性は大いにあります。インスタグラムでは自動検出システムが音源を解析しており、BGMとしてうっかり流れてしまった音楽でも対象となることがあります。
たとえば、「カフェで撮った動画に店内のBGMが入っていた」「テレビの音が後ろで流れていた」など、意図せず拾ってしまった音楽でも検出される場合があります。
こういったケースでは、投稿がブロックされたり、音声部分だけが自動でミュート処理されることも。一度アップしてしまうと通知も来るため、万が一の時はすぐに該当動画を非公開にするか削除しましょう。
確実に安全を守りたいなら、BGMが入りそうな場面では、音声をオフにするか、後からInstagramの公式音源を追加するのがおすすめです。
11-4. インスタに音源を“登録”する方法はあるの?
残念ながら、個人が直接Instagramの公式ライブラリに音源を登録する方法は用意されていません。 Instagramで使える楽曲は、Meta(旧Facebook)が契約している音楽レーベルや音源提供元とのライセンス契約によって提供されています。
そのため、一般のクリエイターが自作音源をInstagram内の検索結果に表示させるには、音楽ディストリビューター(TuneCore、LANDR、DistroKidなど)を通じて配信登録し、Metaのライブラリに反映されるようにする必要があります。
具体的には以下のような流れになります。
- 音楽配信サービスにアカウントを作成
- 自作楽曲を配信登録(SpotifyやApple Musicなどに同時配信)
- Metaに連携されることで、Instagramミュージックにも掲載される
この方法は一定の審査があり、確実に登録できるとは限りませんが、インディーズアーティストやクリエイターにはよく使われています。 オリジナル音源を広く使ってもらいたい場合には、こうした手段を活用してみるとよいでしょう。
12. まとめ:安心してオリジナル音源を活用し、魅力的な発信をしよう
Instagramでの投稿に音楽を取り入れると、それだけで動画の雰囲気がグッとよくなりますよね。でも、ちょっと待ってください。音楽には「著作権」というルールがあって、それを知らずに使ってしまうと、大切な投稿が削除されたり、アカウントが制限されたりすることもあるんです。
特にオリジナル音源を使いたい人にとって、安心して使える方法を知っておくことはとても大切です。たとえば、自分で作曲したBGMや、ナレーション、環境音など、ゼロから自分で作った音源であれば著作権の心配は不要です。こうした音源を使えば、他の誰とも被らない「あなたらしい発信」ができるんですよ。
さらにInstagramには、Metaが契約している公式ミュージックライブラリもあります。この中にある音楽は、著作権の処理がされているので、ルールに沿って使えば安心です。でも、ビジネスアカウントや商用利用の場合は、使える曲が限られてしまうので注意が必要ですね。
オリジナル音源以外でも、著作権フリー(ロイヤリティフリー)の音楽を使うという選択肢もあります。これらはYouTubeオーディオライブラリなどで提供されていて、無料で使えるものもたくさんあります。ただし、「フリー=完全自由」ではなく、使用条件(商用OK・クレジット表記など)を確認することがとっても大事なんです。
「ちょっとくらいなら…」と思って勝手に市販の曲を使ってしまうと、それがたとえ一部だけだったとしても、著作権侵害として扱われることがあります。「改変したから大丈夫」と思っても、それもNGになることがあるんですよ。
また、クラシック音楽や童謡などのように「著作権切れかな?」と思っていても、演奏者や編曲者の著作隣接権がある場合もあるので油断は禁物です。使う前に、音源の出どころとライセンスを必ずチェックしておきましょう。
Instagramの音楽使用における著作権ルールを守ることは、「自分の投稿を守ること」でもあります。せっかく心を込めて作った動画が削除されてしまったら悲しいですよね。だからこそ、安心して投稿するために、ルールをきちんと理解しておくことがとっても大切です。
オリジナル音源を活用すれば、あなたの世界観をもっと自由に表現できます。しかも安心して使えるから、投稿するたびにドキドキすることもありません。ルールを守りながら、音楽の力を味方につけて、もっと魅力的な発信をしていきましょう!