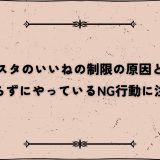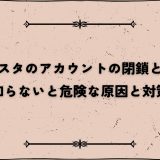「いいねが見えなくなるって、どういうこと?」と疑問に思ったことはありませんか?Instagramでは今、「いいね数を非表示にする」機能を選ぶユーザーが増えています。しかし、この設定が実際にどんな影響を与えるのか、メリット・デメリット、そして適切な使い方までは知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、いいね非表示機能の仕組みや背景から、設定方法、非表示によって変わる投稿画面の見え方、さらにエンゲージメントを保つ工夫までを徹底解説します。
目次
- 1. 「インスタいいね非表示」とは?検索ユーザーが知りたい基本と背景
- 2. 非表示にしたらどう変わる?インスタの表示画面の違いと仕組み
- 3. いいねを非表示にする設定方法【スマホ別・投稿別】
- 4. いつ非表示にするべきか?投稿別に使い分けたい4つのシーン
- 5. 非表示のメリット・デメリット【リアルユーザーの声も紹介】
- 6. いいねを非表示にしても影響しない!エンゲージメントを高める代替手段
- 7. よくある質問・設定ミスを防ぐためのQ&A
- 8. 【比較まとめ】表示すべきか、非表示にすべきか?判断基準とチェックリスト
- 9. 【2025年版】Instagram最新トレンドと「いいね数」に対する価値観の変化
- 10. まとめ|いいね数にとらわれず、自由に発信するSNSライフを
1. 「インスタいいね非表示」とは?検索ユーザーが知りたい基本と背景
1-1. いいね非表示機能の概要と役割とは
Instagramの「いいね非表示機能」とは、投稿についた「いいね」の数を他のユーザーに見せないようにすることができる設定です。
この機能を使えば、フォロワーや閲覧者には「いいね!」の合計数が表示されなくなり、代わりに「○○さん他が『いいね!』しました」といった曖昧な表示に切り替わります。
ただし、投稿者本人は自分の投稿に対する「いいね数」やリアクションしたユーザーの一覧を確認できますので、分析や振り返りに支障はありません。
また、他人の投稿についても、「いいね数を表示しない」ように設定することができます。これは閲覧体験そのものを変える選択で、SNSとの向き合い方をより柔軟にしてくれます。
投稿単位で設定できるため、「見せたい投稿」「見せたくない投稿」を状況に応じて使い分けることができるのも特徴です。
1-2. なぜInstagramは「いいね数を隠す機能」を実装したのか
この機能の背景には、「数字に縛られないSNS体験を提供したい」というInstagramの強い意志が込められています。
「いいね」の数が多い・少ないという比較に苦しみ、自分の投稿に自信を持てなくなってしまうユーザーが特に若年層で増えていました。
そのため、数字による評価を意識せずに、純粋にコンテンツの中身を楽しめる場をつくることが求められていたのです。
また、インフルエンサー文化が発展する中で、「いいね数=影響力」という短絡的な評価軸が定着し、投稿内容よりも数字ばかりに注目が集まる現象も問題視されていました。
この機能はそういった流れを断ち切り、クリエイティブそのものに注目するユーザー体験へとシフトするための一歩なのです。
1-3. 導入の歴史と国際的なテスト展開(例:カナダ・オーストラリアの事例)
この「いいね非表示」機能は、最初から全世界で一斉に導入されたわけではありません。
Instagramは2019年ごろからこの機能の有効性を慎重に見極めるために、一部の国で先行テストを行いました。
テスト対象となったのはカナダ、オーストラリア、ブラジル、日本などの国々で、それぞれの文化やユーザー傾向に応じた反応が注目されました。
例えばカナダでは、「いいね数が見えないことでストレスが軽減された」との声が多く、一方でインフルエンサーからは「仕事の評価基準が不明瞭になった」という意見も上がりました。
オーストラリアでは、ティーン層から肯定的な意見が多数を占めたこともあり、プラットフォームとしては「実装に前向き」との判断に至ったようです。
こうした国際的なテスト展開を経て、現在のような選択制の非表示機能が誕生しました。
1-4. Meta社(旧Facebook)の公式見解と背景にあるメンタルヘルスへの配慮
Instagramを運営するMeta社(旧Facebook)は、この「いいね非表示機能」に関して、ユーザーのメンタルヘルスを守るための措置であると明確にしています。
SNSの中でもInstagramはビジュアル中心のメディアで、どうしても他人と自分を比較しやすい場でもあります。
特に10代や20代の若年層にとって、「いいねの数が少ない=自分に価値がない」と感じてしまう傾向が深刻な問題となっていました。
Meta社はこうした状況に対し、「SNSをもっと安心して楽しめる空間にしたい」という理念を掲げ、非表示機能の導入に踏み切ったのです。
さらにMeta社は、ユーザーが自ら表示・非表示を選べる自由度の高い設計を意識しており、数字を完全に無くすのではなく「気にしたくない人が気にしなくて済むように」するという視点で開発が進められました。
このように、機能の裏にはメンタルヘルスの維持とSNS依存の軽減といった配慮がしっかりと存在しています。
2. 非表示にしたらどう変わる?インスタの表示画面の違いと仕組み
2-1. 投稿者から見える画面と、フォロワーから見える画面の違い
インスタで「いいね数」を非表示にしても、投稿者本人の画面ではこれまで通りいいね数を確認することができます。
投稿詳細画面を開けば、いいねしてくれたユーザー一覧が表示され、何人がいいねしてくれたのかもすぐに把握できます。
つまり、記録としては残っているんですね。見た目だけ、他人に隠されている状態ということです。
一方で、フォロワーや他のユーザーがその投稿を見たときには、
「〇〇さん他が『いいね!』しました」という表示に変わります。
合計のいいね数は表示されず、誰が反応したか一部の名前だけが見える形になります。
これは他人の評価を気にせず、自分の投稿に集中できるように設計されているんです。
2-2. 「○○さん他がいいねしました」とは?表示内容の仕様解説
いいねを非表示にした投稿を見たときに出てくる「○○さん他が『いいね!』しました」という表示、気になりますよね。
これは、自分がフォローしているユーザーや、自分のフォロワーの中から、いいねした人がピックアップされて表示される形式です。
つまり、誰が反応したかはある程度わかるけれど、いいねの総数は出ないという仕様です。
また、いいねしたユーザーをタップしてリストを確認することも可能ですが、全体の数はそこでは分からないため、人気度の判断にはつながりにくくなっています。
この仕組みは、見た目の数字ではなく、投稿の内容そのものに注目してもらうことを目的としています。
2-3. 非表示でも“いいねされた人数”を自分だけが見る方法
「いいね」を非表示にしていても、自分の投稿であれば、いいねされた人数はいつでも確認可能です。
確認方法は簡単。
まず、自分の投稿を開いて「いいね!」部分をタップするだけで、いいねしたユーザーの一覧と合計人数が表示されます。
また、他人の投稿で「いいね数と再生回数を非表示」の設定を解除すれば、その投稿に限り、いいね数が見えるようになります。
この設定は、インスタグラムアプリの「設定とプライバシー」→「投稿」→「いいね数と再生回数を非表示」から切り替えられます。
見えないだけで、ちゃんと数字は残っているというのは、安心ポイントですよね。
2-4. アルゴリズムへの影響は?リーチや発見タブ掲載に変化はあるか
「いいね数」を非表示にしたからといって、インスタのアルゴリズムには直接影響があるわけではありません。
リーチ数や発見タブへの掲載は、投稿の保存数やコメント数、閲覧時間など複数の要素に基づいて決まります。
むしろ、いいね非表示を選択したことで、プレッシャーから解放されて質の高い投稿ができるようになる人も少なくありません。
それによってフォロワーとのエンゲージメントが自然に高まることもあります。
つまり、アルゴリズムよりもユーザーの反応の質が大切なんですね。
ただし注意点もあります。
例えば、フォロワーが「他の人が押しているから押す」という心理で動いていた場合、いいねが見えなくなるとエンゲージメントが下がることも。
特にインフルエンサーや企業アカウントなど、数値が信頼の証になっている場合は、戦略的に非表示と表示を使い分けることが必要です。
3. いいねを非表示にする設定方法【スマホ別・投稿別】
3-1. 新規投稿で非表示にする方法(iPhone・Android対応)
新しくインスタグラムに投稿する際には、事前に「いいね数を非表示」にする設定を行うことが可能です。
この機能は、投稿ごとに適用できるため、投稿内容に応じて使い分けることができます。
設定はiPhoneでもAndroidでも同じ手順で行えますので、以下の方法を参考にしてください。
まず、インスタグラムアプリを開いて新規投稿画面に進みます。
写真や動画を選んでキャプションを入力する画面まで進んだら、「詳細設定」という項目を見つけてタップします。
その中にある「この投稿のいいね数と再生回数を非表示にする」をオンにすれば、投稿後も他のユーザーからはいいねの数が見えない状態になります。
この設定をすれば、「いいねの数が少ないから投稿をやめようかな…」と迷ってしまうこともなくなりますよ。
3-2. 過去の投稿に後から適用する方法
過去に投稿した写真や動画でも、「いいね数」をあとから非表示にすることができます。
つまり、「最初は見せてもよかったけど、やっぱり隠したいな…」と思ったときにも対応できるんです。
方法はとっても簡単です。まず、自分のプロフィールから非表示にしたい投稿を表示します。
右上の「…(三点リーダー)」をタップし、「いいね数を非表示にする」を選ぶだけで完了。
この操作は、投稿ごとに個別に設定する必要がありますが、何度でも変更可能です。
気分やフォロワーの反応に応じて、柔軟に使い分けられるのは嬉しいポイントですね。
3-3. 閲覧時に他人の「いいね数」を見えなくする方法(ユーザー側設定)
インスタでは、自分が見る他人の投稿についても、「いいね数」を非表示にする設定ができます。
つまり、「人気投稿を見るたびに比べてしまってツライ…」と感じている方にとっては、心の負担を減らせるありがたい機能です。
iPhoneでもAndroidでも操作は同じです。まず、プロフィール画面を開き、右上の≡メニューから「設定とプライバシー」を選択します。
次に、「投稿」をタップし、「いいね数と再生回数を非表示」をオンにすればOK。
これで、フィードやハッシュタグ検索で表示される他人の投稿でも、「いいねの合計数」が表示されなくなります。
なお、非表示にしても、誰が「いいね」したかは引き続き確認できますので、フォローしている人の反応が分からなくなることはありません。
SNS疲れを軽減する目的にも、とても効果的な設定です。
3-4. PCからの設定はできる?できない?注意点まとめ
PC版インスタグラムでは、「いいね非表示」の設定変更はできません。
スマホアプリで行った設定内容が、そのままPCにも反映されるしくみです。
たとえば、スマホで「この投稿のいいね数を非表示にする」と設定した投稿は、PCで見ても非表示のままになります。
ですが、PCから投稿した場合は「詳細設定」の選択肢が表示されないため、いいね非表示の設定はできません。
投稿後にスマホアプリから非表示に設定し直す必要があるので、うっかり忘れないよう注意しましょう。
また、PC版では「他人の投稿のいいね数を見えなくする」という閲覧者側の非表示設定も行えません。
設定変更はすべてスマホのInstagramアプリで行う必要があります。
パソコンしか使わない方にとっては少し不便かもしれませんが、スマホから一度設定してしまえば、以降は反映され続けるため安心です。
4. いつ非表示にするべきか?投稿別に使い分けたい4つのシーン
4-1. 承認欲求を手放したいとき:自己肯定感を高めたい場合
インスタグラムを使っていると、つい「いいねの数」に一喜一憂してしまうこと、ありますよね。「前より少ない……」と落ち込んだり、「もっと多くのいいねがほしい!」と焦ったり。でも、本来SNSは自分らしさを自由に表現できる場所。そんなときこそ「いいね非表示」機能の出番なんです。
特に10代〜20代の若年層では、SNS上での評価が自己肯定感に大きく影響することがあります。心理的プレッシャーにさらされながら投稿するのは、正直つらいですよね。いいね数を見せない設定にすることで、「数字=自分の価値」という呪縛から解放されます。
自分が見せたいと思う写真やメッセージを、誰の評価も気にせず投稿できるようになると、本当の意味で「自分を好きになる第一歩」を踏み出せるんです。「いいねに振り回されたくない」「自分の心を大切にしたい」と思ったら、思いきって非表示にしてみてくださいね。
4-2. 炎上・批判リスクのある投稿を控えめにしたいとき
社会的・時事的なテーマを扱う投稿や、自分の意見をはっきり伝える投稿には、どうしても反対意見や批判がつきものです。そんな時、「いいね数が少ない=支持されていない」と誤解されたり、それを根拠に批判が加速してしまうことも。
そこで活躍するのが、いいね非表示の設定です。数字に注目を集めず、あくまで「内容」に集中してもらうためには、視覚的な情報のコントロールが有効です。特にコメント欄を閉じずにいいねだけ非表示にすることで、意見交換の場は残しつつ、不要なネガティブな連鎖を抑えることができます。
たとえば、環境問題やジェンダーに関する投稿、災害に対する想いなど、発信は大切だけど敏感な話題の場合、「いいね数」という不要な評価軸を外すことで、投稿が誤解されにくくなるんです。非表示にすることで「炎上の燃料」となる要素を事前に減らせるのは、とっても賢い使い方です。
4-3. フォロワー数が少ない初期段階のアカウント運用
インスタを始めたばかりの頃や、新しいプロジェクトアカウントを立ち上げたばかりのときって、どうしても「いいねが少ない状態」が続きますよね。その状態を見られるのが恥ずかしくて、投稿をためらってしまうこともあるかもしれません。
でも、それで投稿頻度が下がってしまっては、本末転倒。アカウント成長の初期フェーズでは、まず「発信を継続すること」が最優先です。そのためにも、いいね非表示機能はとても役立ちます。
特にビジネスアカウントや趣味の発信では、数よりも「コンテンツの質」や「継続性」が信頼を作るカギです。いいね数を気にせず、思いきって写真や動画、情報を発信し続けることが、自然なフォロワー獲得につながります。
「誰も見てない気がする…」なんて心配せず、堂々と投稿するために。非表示設定は、スタートダッシュを支えてくれる心強い味方ですよ。
4-4. 企業アカウントでPR色を薄めてユーザー視点を強めたいとき
企業やブランドの公式アカウントを運用している場合、「宣伝っぽい投稿が嫌われる」という課題に直面することがあります。特に最近は、ユーザーの視点がどんどんシビアになっていて、「数字アピール」が逆効果になるケースも増えているんです。
そんな時に使えるのが、いいね非表示の設定です。数字を非表示にすることで、ユーザーはコンテンツそのものに集中しやすくなります。例えば、商品紹介の投稿でも、「いいねが少ないから人気ないのかな?」と思われることを避けられるんですね。
また、ユーザー目線のナチュラルな投稿を意識したい時には、非表示設定によって「企業感」を薄める効果もあります。PR臭を減らすことで、ユーザーとの距離感がグッと縮まりますよ。
数字に頼らず、中身で勝負できる投稿設計を目指すなら、この機能は欠かせません。ブランドの信頼性を高めるためにも、ぜひ活用してみてくださいね。
5. 非表示のメリット・デメリット【リアルユーザーの声も紹介】
5-1. メリット①|他人と比較しなくなり、気軽に投稿できる
いいねの数が見えることで「誰かに評価されているか」が気になりすぎてしまう方は少なくありません。特に10代〜20代前半の若いユーザーは、「いいねが少ないと恥ずかしい」「反応が悪かったら投稿を消したい」といった心理に振り回されがちです。ですが、いいねを非表示にすることで、こうした承認欲求のストレスから解放されます。
例えば、大学生のAさん(22歳)は「友達が何百件も“いいね”をもらってる中、自分は20件くらいで、投稿するたびに比べてしまっていた」と話します。非表示にしたことで、フォロワー数に関係なく、気軽に投稿を楽しめるようになったそうです。「人と比べなくていい」という安心感が、自分らしい表現につながるという実感は、多くのユーザーに共通するものといえるでしょう。
5-2. メリット②|SNS疲れを軽減し、継続的に発信できるようになる
SNSを使っていると、どうしても「投稿しなきゃ」「反応が悪かったらどうしよう」と気を張ってしまい、知らないうちに疲れてしまうことがあります。特に主婦や育児中のママたちの中には、「ちょっとした日常を載せたいのに、見栄えを気にして投稿できない」と感じている人も。
40代のママアカウント運用者Bさんは「家事や育児の合間にスマホを開いて、他のママの華やかな投稿に落ち込むことが多かった」といいます。しかし、いいねを非表示にしてからは、気を遣いすぎずに投稿できるようになり、「共感してもらえたらラッキー」くらいの気持ちで続けられるようになったとのこと。数字に振り回されない運用が、SNS継続の秘訣になるのです。
5-3. メリット③|コンテンツの“質”で勝負する風土が育つ
いいね数が表示されると、つい「数字が多い=良い投稿」と判断しがちですが、それは必ずしも正解ではありません。見た目が派手な投稿や、一時的にバズっただけの投稿が評価されやすくなる傾向があります。
非表示にすることで、ユーザーは投稿内容そのものに注目するようになり、より深いコンテンツや共感を呼ぶ内容が評価されやすくなります。企業アカウントを担当するC社のSNS運用担当者は「一発ウケ狙いよりも、商品の価値やストーリーを丁寧に伝える投稿のほうが保存率や滞在時間が伸びた」と話します。いいねが見えないことで、むしろ“中身勝負”の文化が根付きやすくなるのです。
5-4. デメリット①|インサイト分析がしづらくなる(特にマーケ担当者)
いいね数は、投稿の反響を手軽に測れるシンプルな指標のひとつ。しかし、非表示にすることで、第三者からは投稿のパフォーマンスを客観的に判断しづらくなります。
特にマーケティング担当者にとっては、ユーザーにどう受け取られているかの把握が難しくなり、他アカウントのベンチマーク分析にも影響が出ます。企業アカウントでは、「他社の投稿がどれだけ反応を得ているか」を比較する機会も多いため、数値が見えないことで戦略が立てにくくなるケースがあるのです。
5-5. デメリット②|人気投稿の可視化が難しくなる
インスタのホーム画面や検索(発見)ページでは、人気のある投稿が優先表示される仕組みになっています。しかし、いいねを非表示にすることで、ユーザーがどの投稿に注目が集まっているかを見た目だけで判断できなくなります。
「この人のどの投稿がバズったんだろう?」と気になっても、いいね数が見えないため比較が難しくなるのです。これにより、新規ユーザーにとっては「どんな投稿が伸びているのか分からない」と感じる場面も増えるでしょう。
5-6. デメリット③|インフルエンサー活動に支障が出る可能性
インフルエンサーやクリエイターにとって、いいね数は「影響力の可視化」にあたる重要なデータ。企業とのタイアップや案件依頼を受ける際には、数字で実績を示すことが求められる場面もあります。
30代のファッション系インフルエンサーDさんは、「案件の相談を受けたとき、最近の投稿が全部非表示になっていたことで『効果が見えにくい』と不安視された」と語ります。いいね数を非表示にすると、エンゲージメントの証拠が見えなくなるため、信頼性に影響することも。活動の内容によっては、表示・非表示の使い分けが必要です。
5-7. 【体験談】大学生/ママアカ/企業SNS担当、それぞれのメリット・デメリット比較
最後に、立場の異なる3人のリアルな体験談から、いいね非表示の使い方や感じ方を比較してみましょう。
大学生Aさん:「友達と“いいね数勝負”みたいになって疲れていたけど、非表示にしたら投稿するハードルが下がった。でも、どの投稿が受けてるか分かりにくいのはちょっと不便」
ママアカBさん:「他人と比べるのをやめられて気がラクに。毎日投稿を続けられるようになった。ただ、子育てネタがどれだけ共感されてるのかは、数字が見えたほうが分かりやすいかも」
企業SNS担当Cさん:「ブランドの価値を伝える投稿は数字より内容重視。ただ、非表示にするとキャンペーンの盛り上がりが伝わりづらくて、場合によっては『表示に戻す』こともある」
このように、いいね非表示は精神的メリットが大きい一方、マーケティング視点では慎重な判断が求められる機能です。自分の目的に合わせて、賢く使い分けるのが成功の鍵となるでしょう。
6. いいねを非表示にしても影響しない!エンゲージメントを高める代替手段
インスタで「いいね数を非表示」に設定しても、それが原因でフォロワーとの関係が薄れてしまうわけではありません。むしろ、いいね以外のリアクションを引き出す工夫をすることで、フォロワーとのつながりはより深く、質の高いものになっていきます。ここでは、実際に効果がある4つのエンゲージメント強化方法を具体的に解説していきます。
6-1. コメントで深いつながりをつくる|具体例つきテクニック紹介
コメントは、インスタで最も双方向性が高いエンゲージメントです。いいねが見えなくても、「この投稿についてどう思った?」と聞かれれば、つい何か返したくなりますよね。
たとえば、料理の写真を投稿したときに、
「どの食材が一番好き?」「あなたならどんなアレンジを加える?」と問いかけるキャプションを加えるだけで、自然とコメントが増えていきます。
さらに、「〇〇さんのコメント嬉しかったです!」など、返信をすることで会話が生まれやすくなります。このようなやりとりは、インスタのアルゴリズムにも好影響を与え、リーチ拡大につながります。
6-2. 保存されやすい投稿の共通点|ノウハウ・チェックリスト系が強い理由
保存は、「この情報をあとで見返したい!」という気持ちの表れ。つまり、保存数が多い投稿=価値の高い投稿としてインスタに認識されやすくなります。
特に人気なのは、ノウハウやチェックリスト系の投稿。たとえば、以下のような投稿が保存率アップに効果的です。
- 「秋服コーデ5選|気温18度の日に迷わない!」
- 「忙しい朝に!5分で完成する時短メイク術」
- 「絶対失敗しない撮影構図チェックリスト」
このように、フォロワーが「実用的だな」と思える内容を意識すると、保存されやすくなります。
6-3. シェアされやすい発信とは?リール・ストーリーズ連携も活用しよう
シェアは、あなたの投稿がフォロワーの「心に刺さった」証拠。しかも、シェアはフォロワーの枠を超えて新しい人に届けるチャンスでもあります。
特に有効なのが、リールとストーリーズの活用です。リールで感情に訴える動画を作り、ストーリーズで「これ、シェアして友達にも教えてあげてね!」と伝えましょう。また、引用されやすい名言や面白い豆知識なども、シェアのきっかけになります。
さらに、ストーリーズにスタンプや投票機能を加えると参加率がアップします。リール・ストーリーズの連携で、シェアを促す導線を強化しましょう。
6-4. ハッシュタグの選定・CTA文の工夫でいいね以外の反応を引き出す
いいね非表示でも、見てくれる人の行動を引き出す工夫はたくさんあります。そのひとつが、ハッシュタグとCTA(行動喚起)文の工夫です。
また、キャプションの最後に「保存して、あとで見返せるようにしようね!」「この投稿、○○な人に教えてあげてね!」とシンプルで優しい言葉のCTA文を添えると、保存・シェアされる可能性が高まります。
いいねが見えなくても、投稿にアクションを促す工夫はしっかりできます。その結果、いいね以上に意味のあるエンゲージメントを生み出すことができるのです。
7. よくある質問・設定ミスを防ぐためのQ&A
7-1. いいねを非表示にしても“バズる”可能性はある?
はい、もちろん「いいねを非表示」にしていても、投稿がバズる可能性は十分にあります。インスタのアルゴリズムは、いいねの数だけで投稿の評価を決めているわけではありません。たとえば、コメント数や保存数、シェアといった他のエンゲージメント指標も重視されています。
特に、最近のインスタでは「いいね非表示」を選ぶ人が増えており、それによって注目されるのは投稿の内容そのものです。面白い、役に立つ、共感できる、という投稿は自然と拡散されていきます。
つまり、いいねを隠しても、あなたの投稿が良ければ評価され、リーチも広がります。バズりたいなら、まずは「中身で勝負」することが大切です。
7-2. 投稿ごとに「見せる・隠す」を自由に切り替えることはできる?
はい、インスタでは投稿ごとに「いいね数を表示・非表示」する設定を自由に切り替えることが可能です。
たとえば、1枚目の写真は「注目を集めたいからいいね数を見せる」、でも2枚目の投稿は「気楽に投稿したいから隠す」といった使い方ができます。しかも、この設定は投稿した後でも変更可能です。
投稿の右上にある「…(メニュー)」をタップし、「いいね数を非表示にする」または「表示する」を選ぶだけで切り替えが完了します。その時の気分や目的に応じて、柔軟に使い分けましょう。
7-3. 自分の「いいね履歴」や反応はどこで確認できる?
いいねを非表示にしても、自分がもらった「いいね数」や反応はきちんと確認できます。
具体的には、投稿の詳細画面を開いて「いいねしたユーザー一覧」を見れば、誰が反応したかや合計のいいね数が分かります。これは投稿者本人だけが確認できる情報で、他のユーザーからは見えません。
また、自分が「いいね」を押した履歴は、アクティビティログや「あなたがいいねした投稿」から確認できます。インスタの設定メニューからチェックできるので、一度のぞいてみるといいですよ。
7-4. 過去の投稿すべてに一括設定できる?(←現状不可)
残念ながら、2025年現在の仕様では、「いいね非表示」を過去の投稿すべてに一括で適用することはできません。
つまり、過去の投稿を非表示にしたい場合は、1件ずつ個別に設定する必要があります。投稿ごとに「…」メニューから「いいね数を非表示にする」を選んでください。
たくさん投稿している方には少し手間ですが、インスタ側がまだこの機能を提供していない以上、現時点ではこの方法しかありません。将来的に「一括非表示」機能が追加される可能性もありますので、アップデート情報をチェックしておくとよいでしょう。
7-5. 自分は非表示設定しているのに、なぜ他人のいいねが見えるの?
これはちょっとややこしいですが、「自分が非表示設定したからといって、他人の投稿も自動的に非表示になるわけではない」からです。
インスタでは、自分の投稿についての非表示設定と、自分が見る他人の投稿に対する非表示設定は、それぞれ別の設定項目です。
他人の投稿の「いいね数」を見たくない場合は、次の手順で設定しましょう。
アプリで:
・プロフィール画面を開く
・右上のメニュー(≡)→「設定とプライバシー」→「投稿」
・「いいね数と再生回数を非表示」をオンにする
これで自分が見るすべての投稿の「いいね数」が非表示になります。一方、自分の投稿の表示・非表示は、投稿ごとに設定が必要です。設定が別々に存在するという点に注意しましょうね。
8. 【比較まとめ】表示すべきか、非表示にすべきか?判断基準とチェックリスト
インスタの「いいね非表示機能」は、自分らしい投稿をしたい人にとって、非常に頼もしい味方です。でも、すべての人にとってベストな選択とは限りません。目的や状況によって、表示・非表示を使い分けるのが最も効果的です。このセクションでは、目的別のおすすめ設定パターンや非表示が向いている人の特徴、さらにまず試してみたい運用方法まで、具体的に解説していきます。
8-1. 「目的別」おすすめ設定パターン(例:趣味投稿/副業/ブランド運用)
インスタの使い方は人それぞれ。「何のために投稿しているのか」という目的に応じて、いいねを表示すべきか、非表示にすべきかが変わってきます。以下に、代表的な3つのケースをご紹介します。
① 趣味や日常の記録として楽しみたい人
このタイプの人は、基本的にいいね数を気にせず、自分の世界を大切にしたい人たちです。非表示設定にすることで、フォロワーからの評価に左右されず、自由に投稿を楽しめます。他人と比べて落ち込むこともなくなり、SNS疲れの予防にも効果的です。
② 副業・個人のスキルアピールに活用したい人
ライターやカメラマン、デザイナーなど、自分のスキルやポートフォリオを見せたい人にとっては、投稿内容が命。数字にとらわれず、作品そのものを見てもらいたい場合は非表示が◎です。ただし、案件獲得など数字を武器にする場面では、投稿ごとに「表示・非表示」を切り替えるのがおすすめです。
③ ブランド・ビジネスアカウントで集客を狙う場合
いいね数は、フォロワーの反応を示す重要なエンゲージメント指標となります。非表示にすると信頼性や人気が見えづらくなり、効果測定が難しくなるため、基本的には「表示」に設定するのが無難です。
8-2. 非表示が向いている人の特徴5つ
どんな人が「いいね非表示設定」に向いているのでしょうか?次の5つの特徴をもつ人は、非表示を取り入れることで、より快適にInstagramを楽しむことができます。
① 数字にプレッシャーを感じやすい人
「いいねが少ないと恥ずかしい…」「誰かに見られてる気がする…」と、ついつい数字が気になってしまうタイプの人。非表示にすることで、心の負担が大きく軽くなります。
② SNS投稿に疲れを感じ始めている人
「投稿した後、いいね数ばかり見てしまう…」という経験はありませんか?非表示にすることで、SNS疲れを和らげることができ、リラックスした投稿が可能になります。
③ 比較や競争が苦手な人
他のユーザーの投稿と自分のいいね数を比較してしまう人には、非表示がぴったり。自分らしさを守りたい人にとっては、安心できる選択です。
④ 表現の自由を優先したいクリエイター
「いいねが多い=良い投稿」という風潮を気にせず、作品の本質を見てほしい人には、非表示設定が効果的。アートや文章、写真など、作品そのものの価値で勝負したい人に向いています。
⑤ フォロワー数は少ないが質を大事にしたい人
「まだフォロワーが少ないから、数字に差が出てしまう…」という方でも、非表示にすることで余計な比較を回避できます。質で勝負する人こそ、いいね数にとらわれない発信スタイルが適しています。
8-3. まずは一部投稿で試す運用方法と検証方法
「いいね非表示って、自分に合うのかよくわからない…」という方は、いきなり全投稿を非表示にするのではなく、一部の投稿だけで試してみるのが安心です。
① テスト対象の投稿を決める
例えば、「日常系の投稿は非表示」「キャンペーン投稿は表示」といったように、目的に応じて使い分けましょう。
② 投稿後の反応を記録する
非表示にした投稿でも、自分は「いいね数」を確認できます。投稿後のエンゲージメント(保存数やコメント数、シェア数など)を比較して、表示あり・なしの効果の違いを見てみましょう。
③ コメントやDMなどの声をチェックする
フォロワーから「いいね数が見えない方が気楽」「逆に気になる」などの反応があれば、それも貴重なフィードバックです。
④ 必要に応じて切り替えを
投稿ごとに表示設定は自由に変えられるので、試してみて合わなければ、また戻せばOK。インスタは自分のペースで楽しむものなので、焦らず自分に合ったスタイルを探していきましょう。
8-4. まとめ
「いいね非表示機能」は、単なる数字の隠蔽ではなく、インスタグラムを自分らしく使いこなすための選択肢のひとつです。目的やアカウントの運用方針に応じて、うまく使い分けることで、SNS疲れを防ぎながら、より良いコンテンツ発信ができます。
大切なのは「どんなふうに見られたいか」よりも、「どんなふうに楽しみたいか」。あなたらしいインスタ運用を、今日から始めてみましょう。
9. 【2025年版】Instagram最新トレンドと「いいね数」に対する価値観の変化
Instagramの「いいね非表示機能」は、今やただのオプションではなく、SNS運用のスタイルそのものを変える象徴となっています。特に2025年現在、Z世代やミレニアル世代を中心に「他人と比べるSNS」から「自分らしさを表現するSNS」へのシフトが急速に進んでいます。このセクションでは、「いいね数」という指標に対するユーザーの意識変化と、海外事例を交えた非表示の活用術、さらに2026年に向けた未来予測までをじっくりご紹介します。
9-1. Z世代・ミレニアル世代の「SNSに求めるもの」はどう変化したか
2020年代初頭までは、「いいね数=評価」という感覚がSNS全体にありました。しかし、2025年現在、その考え方は大きく見直されつつあります。特にZ世代は、SNSを「競う場」ではなく「共感し合う場」として捉える傾向が強く、自分の心地よさを最優先にする使い方が主流となっています。
Instagramが導入した「いいね非表示機能」は、このような時代背景に対応するためのもので、精神的プレッシャーからの解放を目的としています。たとえば、「いいねが少ないから投稿したくない」という声は、これまで企業アカウントや個人運用者の大きな悩みでした。この機能の実装により、フォロワーの反応や数字に一喜一憂せずに、自分の世界観を表現しやすくなったのです。
また、ミレニアル世代では仕事や子育てに忙しい中、SNSに「癒し」や「インスピレーション」を求める人が増加。彼らもまた、いいね数よりも投稿の中身、たとえば「共感できるストーリー」や「役に立つ情報」に価値を見出しています。こうした背景から、「見た目の数字よりも、中身で勝負したい」というユーザー心理がSNS全体に広がっています。
9-2. 海外インスタ運用における「非表示活用術」の成功例
日本国内でも「いいね非表示」が広がっていますが、実は海外では一歩進んだ活用法が定着しています。たとえばアメリカやカナダの一部インフルエンサーは、あえていいねを非表示にすることで、ブランドや企業から「質重視のパートナー」として評価されるようになりました。
一例として、ニューヨーク拠点のファッションインフルエンサーが、投稿の「いいね」を完全に非表示にし、代わりにコメント数や保存数の向上に注力。その結果、ユーザーとのコミュニケーションが増え、ストーリーズでのクリック率も大幅に上昇しました。「数字を隠す」のではなく、「本当に見てほしいポイントを見せる」という発想が、非表示機能の真の活用術なのです。
さらに、オーストラリアでは教育関連のアカウントが、生徒の自己肯定感を育むために非表示を標準運用しています。これは、いいね数の多寡で優劣がついてしまうのを防ぐとともに、生徒が自分のアイデアに自信を持つための工夫。このように、非表示機能は単なる「見せない選択」ではなく、ユーザーとの信頼関係を築くツールとしても機能しています。
9-3. 2026年に向けたインスタ運用の未来予測
これからのInstagram運用においては、「バズるかどうか」よりも、どれだけユーザーと深くつながれるかが重視されていくでしょう。2026年に向けたトレンドとして注目されているのは、以下の3つのポイントです。
① 保存・シェア・コメント重視の運用:Instagramのアルゴリズムも、エンゲージメントの質を重視する傾向にシフト中。特に保存やコメントといった「行動を伴うリアクション」が評価対象になりつつあり、いいね非表示の活用とセットで重要性が増しています。
② ジェネレーション別の運用戦略:Z世代には「共感系コンテンツ」、ミレニアル世代には「ライフスタイル提案型」が刺さりやすい。今後は、ターゲット層の心理と使用傾向に合わせて、非表示設定の有無も戦略的に選択されていくでしょう。
③ 視覚×感情の融合:写真やリールでの表現に、「誰かの役に立つ」「元気づける」要素を組み込むことで、ユーザーとの関係性を深化させる運用が進むと見られます。この際、数字ではなく心に響く体験を届けることがカギとなります。
2026年以降は、「インスタは見せ合いっこじゃなく、支え合う場」という価値観が広がっていく可能性があります。いいね数の表示・非表示をうまく使い分けながら、信頼されるアカウント運用を目指しましょう。
10. まとめ|いいね数にとらわれず、自由に発信するSNSライフを
10-1. 自分らしいSNSの使い方とは?
SNSって、他の人の投稿や反応を見て「自分も頑張らないと」と焦ってしまうこと、ありますよね。でも、本当に大切なのは「あなたがどんな気持ちで、どんな思いを込めて投稿するか」です。インスタグラムでは、2025年現在「いいね数を非表示にする」機能が備わっていて、他人の評価を気にせずに使える仕組みが整っています。
特に10代~30代の女性たちの間では、「いいね数が少ないと恥ずかしい」という感覚から、投稿を控える人も増えているんです。でも、実はいいねを非表示にしても、自分だけはちゃんと確認できるので、エンゲージメント分析はそのままできるのです。「見せたい自分」ではなく、「本当の自分」を表現できるSNSに変えていくのが、これからの上手な付き合い方と言えるでしょう。
10-2. 表示・非表示の選択は「戦略」である
「いいね数を非表示にするのは、ただの自己防衛?」そんなふうに思う人もいるかもしれません。でも実際には、これはれっきとした運用の“戦略”のひとつなんです。
たとえば、企業アカウントやインフルエンサーなら「バズった投稿は表示」「反応が読めない投稿は非表示」など、目的に応じた使い分けがされるようになっています。いいね数を見せないことで、内容や世界観に集中してもらえるというメリットも大きいんですよ。
また、いいねの数で比較されることがなくなると、ユーザーの目線も「数字」ではなく「質」へとシフトします。つまり、投稿の中身そのものに価値を感じてもらえる土壌を作ることができるんです。だからこそ、「表示するか、しないか」は、あなたのSNS戦略を左右する重要なポイントになるのです。
10-3. いいねを非表示にするだけで、あなたの投稿はもっと自由になる
数字が見えなくなると、ちょっぴり不安になるかもしれません。でも、その先には想像以上に「自由な世界」が待っているんです。
「いいねが少なかったらどうしよう」と思って投稿をやめてしまう人が多い中、非表示を選べば、誰の目も気にせず、自分の「好き」を発信することができます。それは、たとえばお気に入りのカフェの写真だったり、誰にも見せたことがない手書きのイラストだったり。反応の数では測れない「あなたらしさ」が、より輝くようになるのです。
そして何より、投稿することがもっと楽しくなる。これは、実際に非表示機能を使っている多くのユーザーが感じているリアルな変化です。SNSに疲れたら、まずは「いいね非表示」から試してみましょう。あなたのSNSが、もっと心地よく、もっと自分らしくなるはずです。